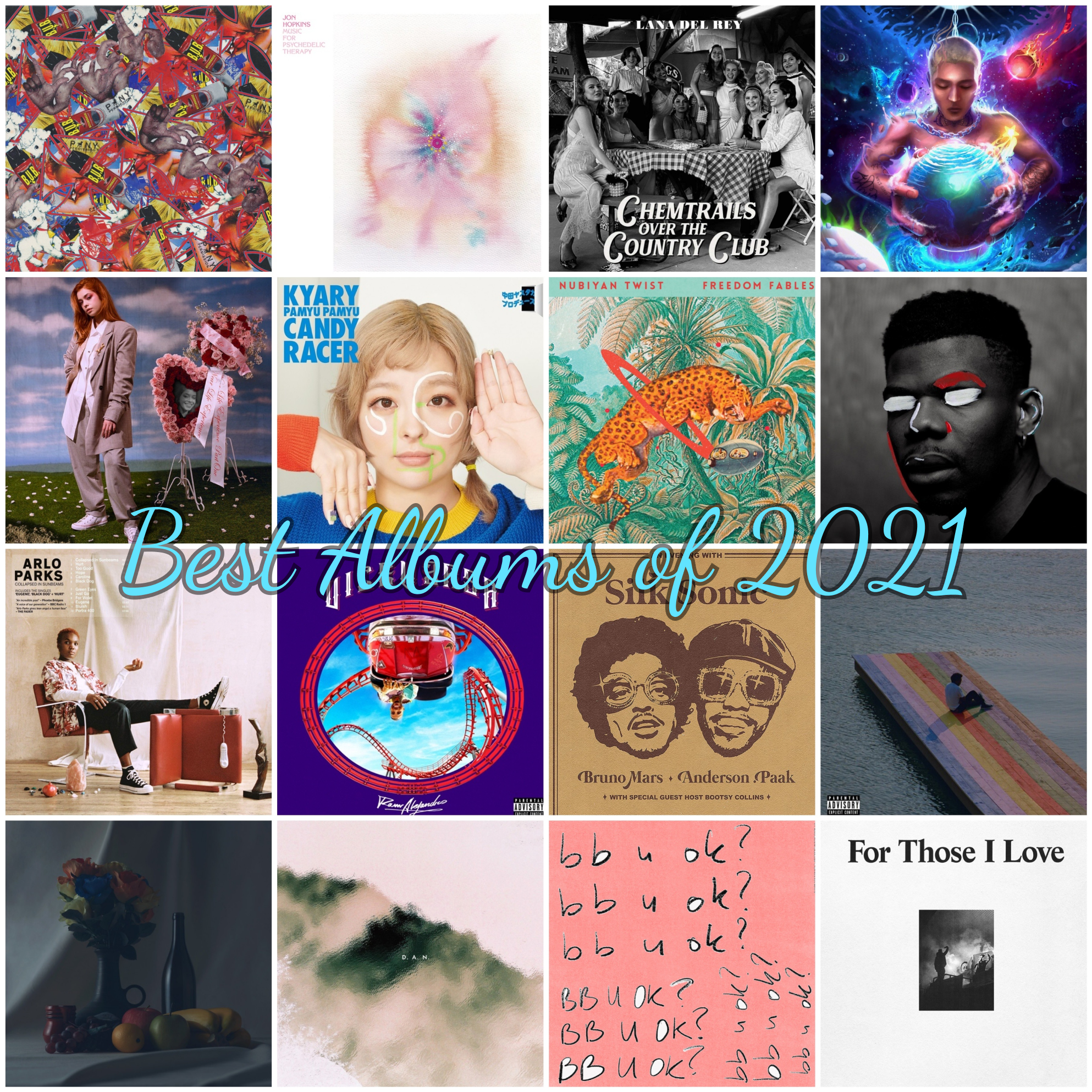2021年は「拡張」と「分裂」の1年だった、とひとまず結論付けておきたい。トラップビートが飽和状態の中その亜流ともいえるレイジビートが盛り上がりを見せ、レゲトンやアフロビーツが北米チャートに押し入るようになり、イギリスのポストロックシーンが何度目かの隆盛期を迎え、アンダーグラウンドのものだったハイパーポップがオーバーグラウンドにのし上がっていく。こうした流れが並列に、 一介の音楽リスナーに過ぎない私のTwitterのタイムラインにも入ってくる。音楽の趣味趣向が広がっていくのを身をもって感じられたのは、ひとまず喜ばしいことだった。
と同時に「中心」のようなものが消えかかっていることもまた同様に確かだった。 先に挙げた音楽ジャンルがすべて漠然と「よきもの」として目に入ったこの1年。出自も発展した経緯も異なり、交わってもいないそれらが同一線上に並ぶことで、今年のランキングはいささか精細を欠いたものになった。加えて自身のメンタルヘルスもラインナップに影を落としている。ワクチンがある程度供給されたと思えば新たな変異株が出現するなど、緊張と緩和の高低差でいえば昨年以上に大きい1年だった。それもあってか、これまで以上に求める作品のテンションもバラつきがある。発散を求める心性と穏やかな暮らしへの希求の間で絶えず揺れながらセレクトされた30枚は、まとまりがなさすぎて自分でも笑えてくる。ただ、平均してみれば似たようなベクトルを持っているようにも思う。そんな具合で、この文章もランキングも混沌の中から立ち現れたものだ。ご了承いただきたい。
本ランキングは2021年12月31日にトップ30のリストを公開し、続いて2022年1月2日~1月31日に30位から1本ずつレヴューを公開する。2021年の30枚、ご笑覧いただければ幸いだ。
30.Wolf Alice『Blue Weekend』

イギリス・ロンドン出身のロックバンドによる、2年9ヶ月ぶり3枚目のフルアルバム。
英国ロックバンドのあらゆるレジェンドに並ぶ作品を作ろう、と思っていたかは定かでないが、聴いているこちらがドギマギするくらい気負いを感じる作品なのは間違いない。前2作ともに全英チャートトップ5入りを果たし、マーキュリー賞を受賞した後なのだ、そう感じたとて不思議ではなかろう。プロデューサーにColdplay『Viva la Vida』やArcade Fire『The Suburbs』などを手がけるMarkus Dravsを迎えた本作は、その甲斐あってかスケール感が増している。全ての音がジワジワとクレッシェンドしていくドラマティックなオープナー”The Beach”や、The Beatles”A Day In The Life”ないしはDavid Bowie”Space Oddity”を彷彿とさせる先行シングル”The Last Man on Earth”などはその成果と言っていい。
しかしその壮大さやバリエーションの豊かさと引き換えに、彼ら固有の特色が見えづらくなっているとも感じた。Ellie Rowsellの透き通る声とそれを増幅させるヴォーカル処理だけが、ギリギリ彼ららしさを繋ぎ止めているような。総合的に見て本作は、中心なき2020年代の音楽シーンを象徴するような作品となった。とは言え、先人たちへの飽くなき憧れがそのまま表出したようなこのレコードを、私は嫌いになれない。
29.Lana Del Rey『Chemtrails Over The Country Club』
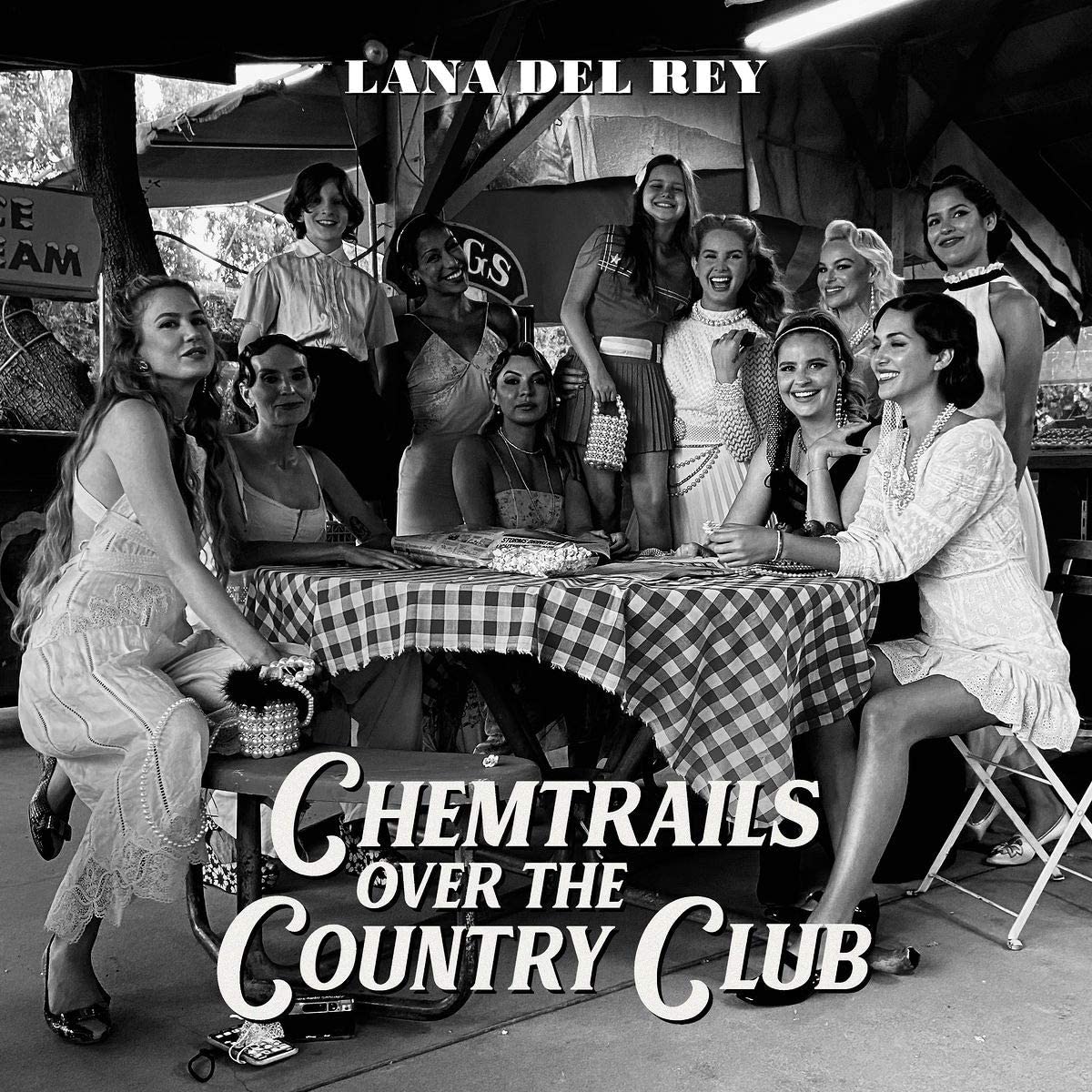
アメリカ・ニューヨーク州出身のシンガーソングライターによる、1年7ヶ月ぶり7枚目のフルアルバム。
自国の歴史すら覚束ない私だ、アメリカ史など尚のこと把握できていない。それでも私がLana Del Reyの作品に惹かれてきたのは、彼女が一貫して欲望について歌ってきたからだ。生物が何かを欲望するとき、倫理や政治的正当性など目に入るはずもない。欲望は選べない。神様だか精子だかが飛ばしたダーツの当たり位置によって、私たちは何かを追い求め続ける。それがどれほど許されないとされるものであろうと。
本作もまた、欲望することそのものの暴力性を描き出している。若かりし頃の経験を描いたオープナー”White Dress”は、音楽業界の男に見出された思い出が語られるが、後にそれは単なる性的搾取に過ぎなかったのだと示される。だが、彼女はその男を糾弾することなく、あまつさえ甘美な思い出として回顧する。そのときは間違いなく、この上ない喜びに満ち溢れていたのだと。ハッシュタグでは括れない、なんなら排斥されてしまう思慕の白熱。ホワイトである自身が特権を得たことの自己反省も重ね合わせながら、それでもなお溢れる愉悦を止めることができない。ピアノとヴォーカルが空間のほとんどを占めるシンプルなサウンドも相まって、あまりに人間的なダブルスタンダードがくっきりと浮かび上がる。
だがしかし、本作はラストのJoni Mitchellカバー”For Free”でそこから飛翔する。ストリートミュージシャン讃歌と言っていいこの曲をもって、これまでの名声や官能、およびそれらを育む土壌となった白人至上主義から降りる覚悟を明確に示した。欲望から降りること、欲望を選択すること、欲望を強化してきた社会の枠組みから逃れること。そうした決意を官能とともに描き出した本作の仮タイトルは『White Hot Forever』だった。
28.24KGoldn『El Dorado』

アメリカ・カリフォルニア州出身のラッパーによる初のフルアルバム。
程よい。程よすぎると言ってもいい。スムースな曲調でありつつ、フロウの高低やフィーチャリングで適度に山場を作り、しかもサクっと聞き終わる。明確なステートメントもノイズィな爆発もほとんどない。総じて、聞いているうちは気持ちいいが、記憶に残るほどのパンチを放っているとは言えない。
ただ、「程よくする」ことに全勢力を傾けているようなムードが、本作を気持ちいいだけの作品にさせない。ストイック。そう、ストイックなのだ。ここで言う「ストイック」はストア派哲学由来の「禁欲主義」を指す。瞬間的な熱狂と、その数秒後にはスワイプされ忘れられかねないTiktokの枠組み。そこで使ってもらうための曲作りが、あまりにも痛切に徹底されている。R&Bのスタイルを使いながらもスクエアなリズムや歌い上げないヴォーカル、何より短尺な曲が彼には多い。そこからは、快楽を超えた強迫的なまでのストイシズムが漏れ出てくる。普段なら鼻白んでしまう「自分の曲をSNSでプロモートしないなんて、怠け者か、無知のどちらかだ」の発言も、ここまでされるとぐうの音も出ない。
27.Tobias Dray『ORANGE Aura』

フランス・パリ出身のプロデューサーによる、8ヶ月ぶり3枚目のEP。
Twitterのフォロワーこそ1000人に満たないものの、Instagramでは14万人、TikTokに至ってはその数300万人(マジで目を疑った)に上る。まさしくインフルエンサーと呼んで差し支えないだろう。と言っても動画はなんてことない様子でダラけている様子やゆるいジョークを切り取ったものばかりで、「俺の目標は全てのSNSをやめること」のテロップとともに紙の箱に入った麺をすすっていたりする。これまでのリリースは全てシングルかEPで、多少のインタヴューやニュースを除けば検索結果は日本で言うところの「いかがでしたか?」系まとめブログばかりだ。ってか日本以外にもこういうのあるんですね。
エレクトロニックも織り混ぜつつベースにインディR&Bがあり、どことなくドリーミーな曲調は、いわゆるベッドルームポップそのもの。しかしながらTikTokでの振る舞い同様、曲調に陰鬱さやシリアスさはほとんど皆無。そこにあるのは解放のフィーリング。ベッドルームの中にいながらも、うっすらだが明確に、目線は外に向けられている。作ったらすぐ出すリリース体制も含めて、コロナ禍における生活史的な1枚。
26.Poté『A Tenuous Tale Of Her』

セントルシア島出身のプロデューサーによる、1年9ヶ月ぶり2枚目のフルアルバム。
カリブ海で生まれ、UKを経て現在はフランス・パリを拠点とする彼。Bonobo主宰のレーベル『OUTLIER』からのリリースとなる本作は、タイトルとは裏腹に自伝的な印象を受ける。リズムが空間の大部分を占めるトラックには、彼が巡ってきた土地の空気をこれでもかと詰め込むように、アフロビーツやレゲトン、ジャングルにUKガラージなどが複合的に折り重なっている。ただし全般にローが強調されているためまとまりはあり、ダンスミュージックとしての風合いが色濃い。祝祭的なビートはクラブで味わう開放感をより強めるはずだ。
対してリリックは非常に内省的で”Stare”では自身の閉所恐怖症が、”Open Up”では不安に駆られる様子が綴られている。パンデミック禍のドキュメントと取ってもいいが、高揚感を煽るビートも含めて考えるなら、クラブという閉鎖空間がもたらすネガティヴな効用をもキャプチャーした、と取っても不思議はないだろう。本来もっともピースフルであるべき空間の陰と陽の両面を、自己探求を通じて描き出した快作。
25.Arlo Parks『Collapsed In Sunbeams』

イギリス・ロンドン出身のシンガーソングライターによる、初のフルアルバム。
どんな時代のどんな地域で生まれ、どのような環境で育ちどのような決断を行ったか。その人を規定するのは畢竟、それぞれに固有の環境や決断でしかない。であるならば、同じ年代というだけで精神的な傾向や趣味趣向を推し量り、あまつさえ全世界規模でのラベリングを試みる、そんな営みに果たしてどれほどの意味があろうか。Arlo Parksは2022年1月現在21歳だが、本人もインタヴュー等で否定しているように「Z世代」を背負う気など更々ないことが楽曲からも窺い知れる。
というのも、彼女が紡ぐリリックはどれも具体性に溢れたものばかりだ。ツイン・ピークス、ヌジャベス、トム・ヨーク、ロバート・スミスなど影響を受けたであろう人や物の固有名詞だけでなく、友人の名前が(恐らくは実名のまま)飛び交ったりする。彼女が生きた日々の情景を空間まるごと活写するような言葉選びが本作の特徴だ。
だが、それらのリリックが単なる内輪ノリに留まらないのは、そして彼女が望まずして「Z世代の代弁者」などと呼ばれてしまうのは、その声や音があまりに親密さを帯びているからだ。ロウでオーガニックな楽器の響き、揺れやズレを拒まないR&Bの意匠、友に語りかけるような(実際に語りかける場面もある)彼女のか細く、しかし「あなた」にだけは確実に届く声。個人と「みんな」を架橋するマジックは、まさにこの点にある。忘れてはならない。あらゆる「ポップミュージック」はまず先に個別の事象が存在する。それを然るべき音で鳴らした時に、暴力的なまでの普遍性が生まれるのだ。どいつもこいつも、順番が違う。
24.NOT WONK『dimen』

北海道出身のロックバンドによる、1年7か月ぶり4枚目のフルアルバム。
名は体を表す、という言葉がある。音楽にもそれは言えると思っていて、優れた作品であればあるほど、タイトルやアートワークと鳴ってる音が紐付けられる事が多い。「このアルバムは水色のイメージだなあ、ってかそもそもジャケットがそうじゃねぇか」となることがしょっちゅうだ。本作もまさにその系譜に位置している。1組の手に色とりどりのマニキュア。輪郭のはっきりした撮り方。聴いた人ならわかるだろう、こんなアルバムだという気がしないか?
まずもって冒頭”spirit in the sun”からしてこれまでの彼らと違う。ハンドクラップに始まりエレピとともにドリーミーな展開で始まったと思ったら、1分と経たずにリズム隊の音がグッと前に出てくる。しばらくするとシューゲイザーと見紛うほどのギターの洪水が襲い、一瞬の後、静寂とともにフォーキーなストロークを残して終わる。なんなんだこれは。パンキッシュな出だしから唐突にサックスが入りジャズの様相を見せる”slow burning”然り、複数の音楽ジャンルを混ぜることなく歪なまま接続させる、ビートスイッチと言っていい急展開を持った曲が多くある。
文章に起こすと単にグチャグチャしてるだけの作品に聞こえるかもしれないが、それでも本作はトータリティを保っている。理由は音圧だ。どの曲も楽器の圧が強い。他のパートを食うギリギリのラインまで音の幅が拡張され、存在感を見せつけ合うようなフォルムを形成している。各々の存在を殺さず、多くのジャンルを直線上に繋いだ本作は、1人の中に潜むいくつもの「あなた」、ないしは1つの街に暮らすそれぞれの「あなた」を収めたようだ。そんな多面性に満ちた本作は各々の存在を確かめるように、輝きを祝福するように”your name”で幕を閉じていく。
23.Park Hye Jin『Before I Die』

韓国出身、LAを拠点に活動するシンガー、プロデューサーによる初のフルアルバム。
音数も少なく隙間も多いトラックに、祈りのように反復される言葉。それが全てだ。ノイズになることを避けるためもあろうが、歌詞がワンフレーズのみの曲もザラにあるくらいに言葉数が少ない。1曲につきイシューは1つまでといった、ミニマリズムの塊とでも言えそうな歌詞が本作の特徴だ。その一つ一つがどれも平易で飲み込みやすいのも聴きやすさに寄与している。反対にビートはシンプルながらソリッドで、特にキックはどの曲も太く粘ついている。落ち着いたピアノのフレーズに4つ打ちの絡む”Let’s Sing Let’s Dance”や、同じく4つ打ちながらその音色や同じく不穏な上モノのせいでガバの様相を呈している”Never Die”などは特にそれが顕著だ。
コロナ禍に入ってから製作されたという本作。それもあってか本作はダンスアルバムでありながら、クラブよりも自室で黙々と踊ることを志向しているように思える。たった1人、自らに言い聞かせるように、祈りを染み込ませるように踊る。本作はそのためのBGMだ。ダンスやパーティーが持つ解放のイメージとは真逆のムードがここには宿っている。
22.Nubiyan Twist『Freedom Fables』

イギリス・リーズ出身のジャズコレクティヴによる、2年1ヶ月ぶり3枚目のフルアルバム。 いきなりどこかのフェスに放り込まれたかのような弾けっぷり。大所帯であることも関係しているのだろう、あくまで起点はジャズやソウルにありながらもアフロビートやネオソウル、ファンクなどが渾然一体となって襲ってくる。メンバーにブラジル系のミュージシャンもいるためか、レゲエやダブ、ラテンの要素も開幕見える。
率直に言えばジャズには明るくない。だからこそ、ジャズがここまで雑多に世界各地の音楽を取り込めることも、ここまでハイファイな音像にしていいことも知らなかった。こうした感情を抱かせることこそ、彼らのやりたかったことなのだろう。本作には正直、統一感のようなものはない。「祝祭」の一言にしか共通点を見出せないような、エンターテイメントとしての音楽というのが妥当だろう。だが本作の目的はトータリティの達成ではなくプレゼンテーションにある。これは先入観が付き纏いがちなジャンルに対し、それはとても自由なものだとレプリゼントするためのアルバムだ。
21.LEX『LOGIC』

神奈川県出身のラッパーによる、1年1ヶ月ぶり4枚目のフルアルバム。
「日本のラッパーでRAGEビートを乗りこなす奴が出てきた!」という素朴な興奮を抜きにしても”LASER”は本作の、なんなら2021年に日本でリリースされた楽曲の中でも白眉と言っていいだろう。背景一帯を支配するシンセに細かく繰り出されるトラップビート、エモーショナルなメロディから繰り出されるリリック。そのどれもが簡潔で、しかし嘘がない。FAILY TAILのナツと自身を重ね合わせ「仲間と上に行く、余計な奴らはいらない」と宣誓するポジティヴなヴォーカルは自分には少し眩しいが、それが本作全体のムードだ。鬱屈の発散を背景に持つRAGEビートの成り立ちとは裏腹に、”LASER”を含めた全ての曲が一貫して陽のヴァイブスに満ちている。
とは言え曲調はバラエティに富んでいて、ネオソウルなギターのカッティングが心地良い”Without You”や浮遊感あるエコーのかかったヴォーカルに太いベースがコントラストを演出する”ARE WE STILL FRIENDS?”、グランジなショートチューン”No.1″など様々だ。多彩なトラックのそれぞれに硬軟織り交ぜたフロウでLEXは対応していく。どんなビートにもノレるし、どんなテイストの楽曲でも伝えたいことはブレない。バラエティ豊かな本作に”LOGIC”ー筋道と名付けたのは、全くもって理に適っている。
20.Kacey Musgraves『star-crossed』

アメリカ・テキサス州出身のシンガーソングライターによる、3年3ヶ月ぶり4枚目のフルアルバム。
本作を聴いたのは12月頃で、親友と呼んでもいい人からSNSを諸々ブロックされて間もない時期だったと思う。向かい合っての喧嘩をしたワケじゃないし、連絡手段も完璧に途絶えてしまったから、何が気に障ったかはわからないまま。恐らくTwitter上での私の発言に気分を害したんだろうけど、彼の許せないものの形がはっきりしたんなら、それはそれで悪くない終わりかも、と思ったりする。
〈完璧な夢から覚めて、暗闇が訪れた/私は昨日、書類にサインしたんだ〉と打ち明ける冒頭から明らかなように、本作は彼女自身の離婚経験と、そこからの自己回復がモチーフとなっている。私が本作を聴いて惹きつけられたのも、まさにこのテーマが理由で。良き妻になりたくてもなれなかった自身を嘆く”good wife”から、変わらない自分も抱えてもう振り向かないと宣言する”there is a light”に至る道筋は、私が辿るべきそれを示してくれたようでもあった。
私が本作の示した道を歩むためには、まだ時間がかかりそうだ。けど、少しだけ言葉を置いておく。私たちの輝ける時代は終わってしまった。私は変われなかったし、結局離ればなれになってしまったけど、あなたは今も紛れもなく私の一部だと、読まれないであろうこの場所に書き留めておく。
19.PinkPantheress『to hell with it』

イギリス・ロンドン在住のプロデューサーによる、初のフルアルバム。
聴いたことのあるもので、聴いたことのないものを作る。誰でもできることで、誰にもできないものを作る。音楽に限らず、創作に触れる際1番胸が踊るのは、そんな作品に触れたときだ。本作に初めて接したときも、一つ一つのジャンルや具体的な楽曲のサンプルに対する既視感よりもそのワクワクが上回った。
なんだかんだよく聴いているドラムンベース。ジムノペディの旋律。要素それぞれを取り出せばなんら新しさはない。しかしそれらに気だるげな声と内省的なリリックが乗り、1〜2分でスパッと終わるとなれば話は別だ。あまりに唐突に始まり、あまりに唐突に終わる楽曲群はそれ故にオリジナルでスタンドアローンだ。ダンスミュージックが持つ長時間の反復による快楽もなければ、ジムノペディのインスピレーション源となったギュムノパイディアのモチーフも背負わない。歴史とか文脈とかをまるで気にもとめない暴力的なまでの発明が、20歳そこそこの女性のベッドルームから生まれている。これは誰もがなし得たハズの、しかし誰もできなかったサウンドの形。
18.Jon Hopkins『Music For Psychedelic Therapy』

イギリス・ロンドンを拠点とするプロデューサーによる、3年半ぶり6枚目のフルアルバム。
前作『Singularity』から瞑想がテーマとなっていたが、本作は本格的に『幻覚セラピーのための音楽』とタイトルから銘打っている。そう聞くと静的なもの、退屈なもの、何のためにやっているのかいまいちわからないもの……といったイメージが付き纏うが、本作から受ける印象はやや異なる。
Jon Hopkinsがアマゾンの地下洞窟で3泊4日を過ごした経験から生み出された本作。前半こそ洞窟で録音した床の響きや川のせせらぎ、鳥の鳴き声などの自然音がチルい感じで取り入れられているが、後半からそれらの音は後景に退くか完全に消失し、代わりに陶酔感はありつつも厚みを伴ったシンセの音が遠くまで伸び、唸るベースが常に地を這うようになる。曲が進むにつれて「アンビエント」とか「セラピー」といった語のイメージからことごとく逸脱していくほどに、それぞれの音が立体的に配置され、何よりエネルギッシュな展開を見せていく。加えて、自然音についても曲が進むにつれて音量が上がっていき、洞窟のなんてことない反響音すら轟音のように感じられてくる。もし可能ならいいスピーカー、ないしはヘッドホンで聴いてほしい。音楽というより、空間をまるごと作り上げたと言う方が近いくらいの没入感が待っているハズだ。
17.Rauw Alejandro『VICE VERSA』

プエルトリコ出身の歌手・ラッパーによる、7ヶ月ぶり2枚目のフルアルバム。
模索中なんだな、と感じるアルバム。というのも、各曲のテイストにバラつきが見られたからだ。勝負をかけるため、オリジナリティよりもリリースペースで勝負したのかも、なんて邪推も脳裏をよぎる。自身でプロデュースした楽曲が前作より少ない点もそうした予感を助長する。もしくは単にチャートへ迎合するために保険をかけたのかもしれない(それができるだけで超すごいんだけど)。そう感じるくらいに一部の楽曲を除きほぼレゲトンのリズムで攻めていて、それらは正直平板だ。だが残りの”一部の楽曲”の破壊力が凄まじい。なんといっても冒頭の”Todo De Ti”。80sポップスのいい意味で安っぽい質感に跳ねるリズム、そして歌い上げる箇所とスタッカートする箇所が混ざったメロディを乗りこなすヴォーカルの自力の強さ。このテイストにスペイン語が乗っかる新鮮さを含めて、アルバムを通しで聴いてもいいと思わせる力がある。ディスコ風味の”Desenfocaó”やヴァース間を唐突なアーメンブレイクで繋ぐ”¿Cuándo Fue?”などレゲトンの枠に留まらない楽曲のクオリティが軒並み高いので、次は保険なんかかけずにぶっ飛ばしてほしい。
16.L Devine『Near Life Experience Part Two』

イギリス・ニューカッスル出身のシンガーソングライターによる、4ヶ月ぶり4枚目のEP。本作は2021年に連続リリースされた『Near Life Experience』シリーズの第2弾で、その前の作品は2018年に遡る。
「ダンスフロアで死にたい!!」EP冒頭で放たれる痛切な一言やアートワークの雨雲に、未だ光の見えない中で生きる私たちの息遣いが宿っている。そしてそれは特別な誰かではなく、あくまでいち生活者としての視点だ。私たちと同じようにダンスフロアの復活を願い、私たちと同じようにコーヒーを飲みながら退屈な日々を過ごし、私たちと同じようにGeniusに歌詞の注釈を書き込む(アーティスト本人も書き込みできるのねこれ)。曲調はディスコであったりエレポップであったり弾き語りであったりと幅広いが、気だるげなヴォーカルがミックスにおいて大きめに設定されていることもあり、そのどれもがすぐそばで歌っているかのような心地よさだ。労働以外でのコミュニケーションが希薄になった時代に、(たとえあなたがニューヨーカーでなくとも)誰もが誰かの親愛なる隣人なのだと思い出させてくれるような1枚。
15.Baby Keem『The Melodic Blue』

アメリカ・カリフォルニア州出身のラッパーによる、初のフルアルバム。
Kanye West『Donda』に参加し、1stアルバムにしてRosalía、Don Toliver、Travis Scott、果てはKendrick Lamarと組んでいるBaby Keem。果たしてその正体はKendrickが設立した会社『pgLang』に所属しており、なんなら彼の従兄弟だ。その境遇や実績に恥じないアルバムだと思う。
Kendrickをフィーチャリングに迎えた(そして彼にとって久しぶりの楽曲参加である)”family ties”からしてエネルギーが漲っている。安っぽい正義をその場で表明するだけして後に何も残さない連中に唾を吐くKendrickに対し、公営団地で生き残った自らの境遇を語るBaby Keemは、フロウの引き出しと瑞々しさにおいてKendrickと並ぶどころか出し抜いてすらいる。そう、Baby Keemはそもそも何もない場所から這い上がり、その身と行動をもって前に進んできた人物だ。本作で多用されるビートスイッチのごとく、状況が如何に変わっていこうと彼はアクションをやめない。その〈木を育てる、種を植える、息をさせる〉(“issues”)姿勢こそがリリックの内容にも、カラフルながらどのトレンドからも半歩ほど遠いビートの数々にも表れている。
14.Silk Sonic『An Evening With Silk Sonic』

Bruno MarsとAnderson.Paakを中心としたユニットによる、初のフルアルバム。
果たしてこれはノスタルジーに塗れた回顧厨のためのアルバムなのか?自分にはそうは思えなかった。確かに、Bootsy CollinsやLarry GoldなどのR&B〜ディスコにおけるレジェンドを召喚した布陣を見ればそう感じるのも無理はない。しかし同時に本作は”After Last Night”にThundercatが、”Fly As Me”にBig Seanが参加しており、モダンな手触りも十分に感じられるのだ。そのため本作は「70年代R&Bサウンドを完全再現!」の一言で括れるような単純なサウンドになっていない。リムショットのバリエーションやそもそものスネアの鳴り、コーラスワークの若干の忙しなさなども含めて、むしろ「R&Bをやろうとしたけどなんかよくわかんない着地になった」という印象が強くなっている。
メンバー各自のルーツすら違うのにそれでも本作が気持ちいいのは、皆が享楽的なユートピアの構築に全神経を傾けているからだろう。下心を隠せない、ひたすらに情けない、でも底抜けに楽しいひとときの創出。異なるフィールドの猛者が生み出した本作はまさに、愛すべき歪な紛い物であり、それゆえ永遠には続かない。31分という収録時間と『Evening』の名は、これ以上ないほど相応しい。
13.Roosevelt『Polydans』

ドイツ出身のシンガーソングライター・プロデューサーMarius Lauberによる、2年5ヶ月ぶり3枚目のフルアルバム。
音楽を、そして音楽が鳴る場所を愛する人にとって、過去を懐かしむことと未来を夢想することはもはや同義になった。少なくともここ数年は。未だダンスフロアに満杯の観衆を詰め込むには至らず、なんなら以前の活況は2度と戻らないかもしれない。私たちが抱く素朴な欲望は、明日への糧であると同時に「かつてあったもの」に対する思慕でもある。両者が共存することになんの矛盾もない。
Dua Lipaが放った傑作『Future Nostalgia』に続く陽性のダンスミュージック集は、この上ない解放感と郷愁を同時にフラッシュバックさせる。しかし本作は聴いたときに感じる肉体性とは真逆に、作曲はもちろん、すべての楽器の演奏・ミックスまでMarius本人が行った作品でもある。そのうえ、生楽器はいっさい使用していない。環境がそうさせた面も大きいだろうが、彼の作品にしては過剰なまでにコントロールフリークだ。〈続けることはそんなに難しくないよ〉とノスタルジーたっぷりな音像に乗せて歌う裏には、「踊れる日々を取り戻したい」といった欲求の発露が見え隠れする。そりゃそうだ、私たちが辿り着かねばならない、帰らねばならない場所は、このアルバムの中にこそあるのだから。
12.きゃりーぱみゅぱみゅ『キャンディレーサー』

東京都出身の歌手による、3年1ヶ月ぶり5枚目のフルアルバム。
Charli XCXを魅了しSophieと楽曲を製作した彼女を、今ここでHyperpopの祖と呼ぶことになんの抵抗もない。10年前、それだけエポックメイキングで現在の音楽シーンに影響を与えた彼女(と中田ヤスタカ)だが、前作『じゃぱみゅ』では次の一手を模索していたように思う。単純な話、世界の音楽シーンが彼女の表現する音像に追いついてきたのだ。その風向きへの回答として、ハイクオリティながらもモノトーンな『じゃぱみゅ』は存在した。対して、引き続き模索中ではあるものの糸口は見えたな、と感じられるのが本作だ。
序盤からして、フロアライクでハードなダンスチューンが並び、これまでとの違いを強調する(2・3・7拍子からガバキックへ繋ぐ”DE.BA.YA.SHI 2021″が最高)。しかしより意欲的なのは後半。歌謡曲なメロディにVaporwaveなエコーをかけたシンセが乗る”夏色フラワー”などが象徴的だが、かわいさをプレゼンテーションしながら既存の「かわいさ」を諧謔的に嘲笑う手つきが本作には満ちている。そしてそれは彼女がシーンに登場して間もない頃に見せていた素振り、およびそれを受け取る私たちが感じた異物感と1ミリも違わない。『キャンディレーサー』のサウンドが大きく”原点回避”したことは間違いない。しかし根底にあるマインドは、紛れもなく10年前のそれと同じものだ。
11.TurnStile『GLOW ON』

アメリカ・メリーランド州ボルティモア出身のバンドによる、3年半ぶり3枚目のフルアルバム。
いや、ハードコアではあるのだ。ティーンエイジャーが初めてエフェクターを買って鳴らしたようなディストーション、ゴリ押しのコード進行、クリーンながらも絶唱するヴォーカル。雛形は間違いなくハードコアのそれだ。だがどうだろう、この全体をうっすらと支配するドリーミーなシンセは。”BLACKOUT”のアウトロで突如立ち現れるトライバルなパーカッションや”Don’t Play”で顔をチラつかせるラテンのリズムは。折衷とも言えないまだらな他ジャンルの接着は、音楽が自由だったことを思い出させるとともに、ハードコアという自身のホームをそれ以外のフィールドに届ける役目も果たすだろう。かつてTest Iciclesというパンクバンドを組んでいたBlood OrangeことDev Hynesが2曲で関わっているのも頷ける。自らの音楽をサラダボウルのサラダよろしくぐちゃぐちゃにかき混ぜるのではなく、むしろ俺たちはボウルなんだと示す1枚。
10.さかいゆう『thanks to』

高知県出身のシンガーソングライターによる、10ヶ月ぶり7枚目のフルアルバム。
2021年最初の衝撃だった。新曲と既存曲の新録やライヴバージョンなど、2020年の歩みを総合的にパッケージしたドキュメンタリー的な1枚。その第一声は〈戦火の街〉という一言で始まる。数々のヒット曲を手掛けた売野雅勇のペンはサビで更に冴え渡り〈死ぬのはいつでも他人と思ってる 僕らの生き方を問う〉とまで言い切る。今この時代に戦争をテーマにすることは、コロナ禍を描写することとニアリーイコールだ。さかいゆう本人の作詞も含めて本作は言葉の、メッセージのアルバムであり、それを歌い上げる声のアルバムでもある。声を活かすためでも状況のせいでもあるだろうが、ピアノ1本の弾き語りが多いことも大きな特徴だ。
先に歌詞を挙げた”崇高な果実”こそ社会性が全面に出たものだが、フィーリングとしてはLOVEが前面に満ちている。リード曲の”BACKSTAY”はもちろん、新録された”Magic Waltz”や”井の頭公園”も大切な他者との親密さについて書かれた曲だ。ただそのどれもが、誰にとっても困難な現代にあって「よりよく在る」とは何かについての考察であり、思考の軌跡を描いている。
9.D.A.N.『NO MOON』

東京都出身のバンドによる、3年3ヶ月ぶり3枚目のフルアルバム。
聴いている間『DEATH STRANDING』と『DUNE 砂の惑星』が脳裏を過ぎった。美しいものもあるはずなのに、全体を見渡すとただ荒涼とするばかりの風景。あるいは決定的な繋がりを欠いたまま、それでも動き続ける世界のシステム。今ここを舞台とはしていないSFでありながら、その時々の社会の在り方を明確に反映させた2作品と本作には通じるものがある。
サウンドはいよいよ国籍不明・住所不定の様相が色濃い。スペーシーなシンセベースと砂漠の上を滑るようなスティールパンが混ざり合う”Anthem”。複雑なビートからMIRRRORのTAKUMIによるラップを挟んで四つ打ちへと急展開していく”The Encounters”。チェロが全体を牽引するインタールード群。曲の引き出しに伴い、櫻木のヴォーカルもメロウに浮遊するものからラップよろしく言葉数を詰め込むものまで幅が広がっている。全体をガッチリと結ぶのは、夢見てなどいない現実が眼前にあるのだという認識だ。本作はそんな世界を前にして〈どうする?〉と問いかけて幕を閉じる。彼らも含めて全員が、今もなお藪の中を歩いている。それでもどうしようもなく、未来は僕らの手の中にあるのだ。
8.Anonymous Club『SCREENSAVERS VOL 1』

ニューヨークを拠点とするクリエイティヴプラットフォームによる初のフルアルバム。
Hood By Airなるブランドのデザイナー、Shayne Oliverが立ち上げたスタジオ兼プラットフォームで、アート作品の創作やインスタレーションなど多彩な表現を行い、その一環に音楽活動も含まれている様子。Yves Tumorもプロデュースに関わっている。固定メンバーもいるが全体としては流動的で、その時その時に仕事をしたい相手とコラボレーションしている、らしい。公式サイトやBandcampのアーティスト紹介ページ、いくつかのニュースサイトを漁っても出てくる情報はこの程度。Youtubeの登録者数も2022年1月25日現在で580人、唯一アップされているMV”Permission”の再生回数は2306回しかない。
メタリックなサンプルが空間の多くを占めながら、唐突に差し込まれるグランジ的な展開やエモーショナルなメロディはエモラップのそれを感じさせる。だがとにかく無軌道で、メロウなパートのすぐ後に速度を上げることもある。個人的には、まだ各々の活動が活発化する前のOdd Futureを思い出し、勝手に胸を躍らせている。
7.Mdou Moctar『Afrique Victime』

ニジェール共和国出身のギタリストによる、2年2ヶ月ぶり5枚目のフルアルバム。
生まれは西アフリカ、ルーツは遊牧民のトゥアレグ族。歌詞はタマシェク語。正直、私はここまで情報に何ひとつピンと来なかったし、今も来ていない。ここまで耳馴染みのない単語ばかりで萎縮した人もいるかもしれない(と願っている)。だがその実、鳴らされるのはパワフルなロックだ。ただ、いわゆる欧米的なハードロックのそれとは手触りが違っている。トリル奏法の多用によってアラビアンな猥雑さが強調され、ポリリズムを乗りこなす演奏により陶酔感がじわじわと上昇していく。加えてどの曲もBPMが早いため、気がつくとグルーヴの熱に取り込まれてしまう。また、メンバー全員がアンサンブルを重視しているため、サイケデリックな景色が広がりながら統率も取れているという、ありそうでなかった体験が立ち上がるだろう。初めて聴いた類の音が多かった2021年だったが、ロックバンドでそれを感じたのは彼らだけだった。
6.San Holo『bb u ok?』
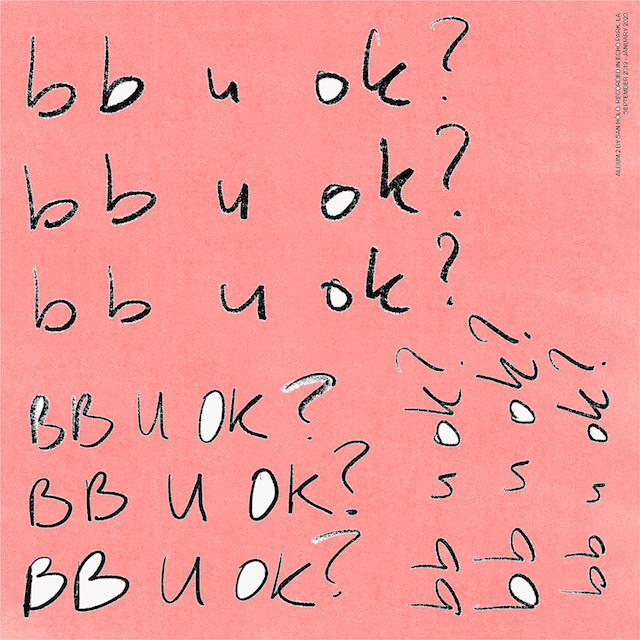
オランダ出身のDJ・プロデューサーによる、2年半ぶり2枚目のフルアルバム。
ビルド&ドロップとアコースティックギターのフォーキーなストロークが、浮遊感あるヴォーカルと硬質でスクエアなキックが、アンビエンスとエモが、プライベートとソーシャルが、なんの違和感もなく手を取りダンスする世界。内省と解放を共に描く点において、EDMの文脈からはまるでかけ離れたように見えるWeezerやAmerican Footballの参加も理にかなっている。あらゆる要素が均等に混ぜ合わされているため、何かが中途半端であるイメージも浮かばない。加えて、よく考えればかなりハイコンテクストなのに聴いた感じはどこまでも軽快なポップソング集。これ以上望むべきものが何も考えつかないし、これさえ聴いていればどんなフィーリングにも程よくマッチしそうだとすら思う。ポストEDM?バカ言うな、これは”””全部”””だ。
5.Mustafa『When Smoke Rises』

カナダ、トロント出身のシンガーソングライターによる、初のフルアルバム。
上記の通り本作が1stアルバムでありながら、Jamie XXやSamphaなど錚々たる面々が参加し、プロデューサーもKanye WestやTravis Scottなどを手がけるFrank Dukes。ここまでのコネクションを持つに至った理由は同郷のポップスターが原因だ。元々彼は詩人なのだが、その詩をDrakeがInstagramでポストしたことにより、Mustafa自身にも注目が集まった。そこからCamila Cabello”All These Years”や”She Loves Controll”、Shawn Mendes & Justin Bieber”Monster”などの楽曲製作にも携わることになり、現在に至る。
ポップミュージックのど真ん中で活躍してきたこれまでのキャリアと比べ、本作の聴き口はすこぶる落ち着いて穏やかだ。秋の木漏れ日のようなアコースティックギターやピアノが全体をリードし、どことなく郷愁を誘う音像になっている。しかし本作も同時に「今はいない他者」について語られた作品だ。タイトルの「Smoke」は文字通り煙を指すと同時に、Mustafaも所属するラップクルー、ハラル・ギャングのメンバーであり、2018年に銃弾に倒れたSmoke Dawgのことでもある(アートワークの右側がSmoke)。公営住宅での日々や〈生きて、生きて、生き延びてくれ〉と懇願するリリックの中に私はいない。それでも耳を惹かれたのは、恐らくは歴史に残らないであろう人の記録であるからだ。この世界で確かに生きていた人に向けた悲しみだからこそ、遠く離れた私の胸をすら、本作は静かに打ち続ける。
4.GRAPEVINE『新しい果実』

大阪府出身のロックバンドによる、2年3か月ぶり17枚目のフルアルバム。
どいつもこいつも、勝手に気持ちよくなりやがる。「ニューノーマル」だとかいう響きで体裁だけ無理矢理ポジティヴにした現状に、まんまとヘラヘラしてやがる。俺がレヴューを1本、満足に書き上げられずにいる間に世界は1周半でもしたみてぇだ。ここでも周回遅れの持久走をやるのか俺は。ちゃんと直視しろよ、その『新しい』ってやつを。本当に美味そうに見えんのか?いや、もしくは本当に美味そうに見えてるのかもしれないな。社交辞令がなぜ社交辞令と呼ばれているか、笑顔の裏で人が何を考えているか、リベラルとされている大統領がなぜイラクへの派兵をやめなかったのか、その二重性に悪意なく気付かない人間が、もしかしたら本当にいるのかもしれない。なら時に、会社のミーティングの場で奇声を発したくなったことはないか?親友の、恋人の、我が子の横面を理由もなく張りたくなったことは?やったことはないかもな、俺だってそうさ。だけど自分にも、今生きているこの社会にもそんな側面が少なからずある。そのグロテスクさに吐き気を覚えながら、俺は今日もなんとかまともにあろうとしてるってワケだ。あんたもそうじゃないのか?
3.ピーナッツくん『TELE倶楽部』

原宿在住(?)のVtuberによる、1年ぶり2枚目のフルアルバム。
やり切れなさに満ちている。ストリートなき場所で生まれ花咲いてしまったがゆえに届けたい人に伝わっていない現状や今も同じ場所から叫んでしまっている自分自身に、血管が切れんばかりの苛立ちを覚えている。〈先立つのはキャリアよりも金だ〉のワンフレーズでVtuber視点の拝金主義を描ききりながら、一向に幸せそうじゃない。それが証拠に、先のリリックはぶっつぶれたベースと拡声器越しのようなフィルターで存在感を奪われている。”風呂フェッショナル”の安らぎに一瞬安堵するものの、その前でも後でも描かれるのは一貫してディスコミュニケーションだ。女性ヴォーカリストを何人も配置しハーレムのパロディを演出しながら、誰一人として良好な関係を結べずに終わるのはそんな自身の写し鏡だろうか。各種動画での振る舞いも含め、おどけた道化としてイキる場面が数多いピーナッツくん。だが本作を聴いていると「わかってくれる奴などどこにもいない」という諦念をも同時に感じる。完成度は高いながらも曲調がバラついて散漫なのは、そうした両義性や歯切れの悪い思いを反映したようだ。
2.The Armed『ULTRAPOP』

アメリカ・ミシガン州で結成されたコレクティヴによる、3年ぶり4枚目のフルアルバム。
人力ハイパーポップ、とまずは乱暴に定義づけてしまいたい。ノイズに塗れて潰れたバスドラのキックにドリームポップめいたメロディ、そこに突如フィードバックノイズが割って入るタイトル曲。随所にハードコアの意匠はありつつ、ピーキーなシンセや展開の早さが、既存のそれとは全く異なるサウンドデザインに導いている。
ところで彼らの活動は見えにくい。何枚もアルバムを出していながら、メンバーが何人いてそれは誰なのかが部分的にしかわかっていないのだ。もっと言うと、ファンたちすら本作の音源に参加しているようで、バンドというよりもコレクティヴの趣が強い。過去作品を全てクリエイティヴ・コモンズ・ライセンス付きでフリーダウンロードにしたり、かと思えば『サイバーパンク2077』に楽曲提供したりといった点含め「誰が作ったか」に対する徹底した反発が感じられる。歴史、文脈といった情報の徹底した統制を行ってまで彼らが取り戻そうとしているのは恐らく、音楽を音楽として聴くことの喜びだ。過剰なまでの詰め込みに反してシンプルな願いを込めた本作は、活動スタンスも含めてこの時代への誠実な批評となっている。
1.For Those I Love『For Those I Love』
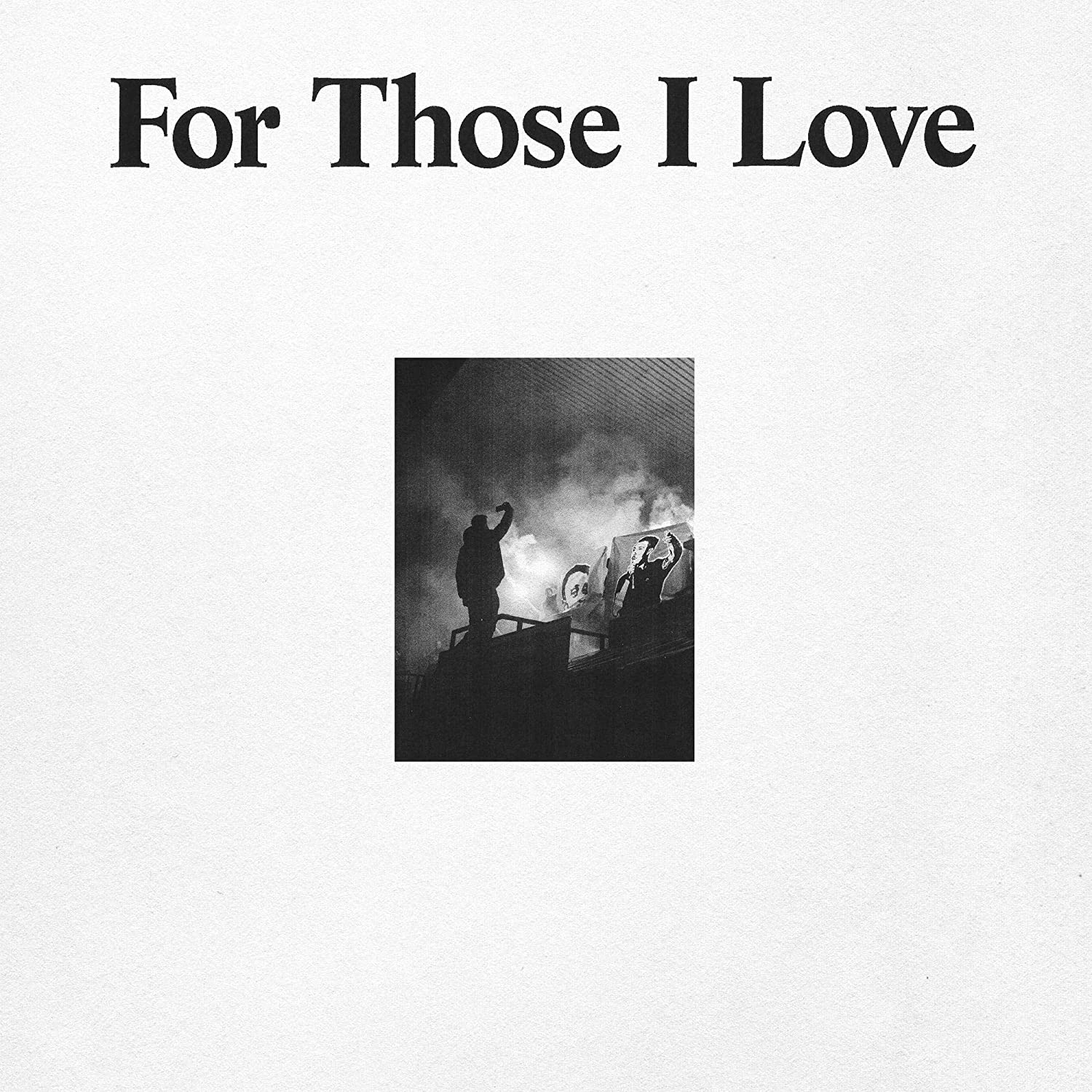
アイルランド・ダブリン出身のプロデューサーによる、初のフルアルバム。
本作で伝えたいことはたった一つしかない。スポークンワードを選択していることも、幅広いジャンルを使い分けながら結局は全曲がダンスビートで占められていることも、たった一言を伝えるための手段でしかない。前者はより言葉を直接的に届けるため、後者は願いの切実さを”反復”というモチーフに託すため。それだけのために全9曲、46分5秒を使っている。祈り、という言葉すら陳腐になるほどの言葉の楔。生々しく荒削りな音響やサンプルの置き方。それが、ダンスミュージック集であるはずの本作を解放とは真逆のムードに引っ張っている。
本作における全ての要素は、人生の多くを過ごした親友であり、共にパンクバンドも結成したPaul Curranに捧げられている。彼は自ら命を絶った。だがこの作品の中にPaulは生きている。誰か1人でもPaulのことを覚えている限り、彼は死なない。その思いの強さを、私たちはときに愛と呼んでみたりする。きっとそれは間違ってない。『誰からも忘れられた時、人は真に死ぬ』。ひどく手垢のついた考えを誰よりも大切に握りしめて、David Balfeは何度も力強く宣誓する。〈私には愛がある。 決して消えることのない愛が。〉